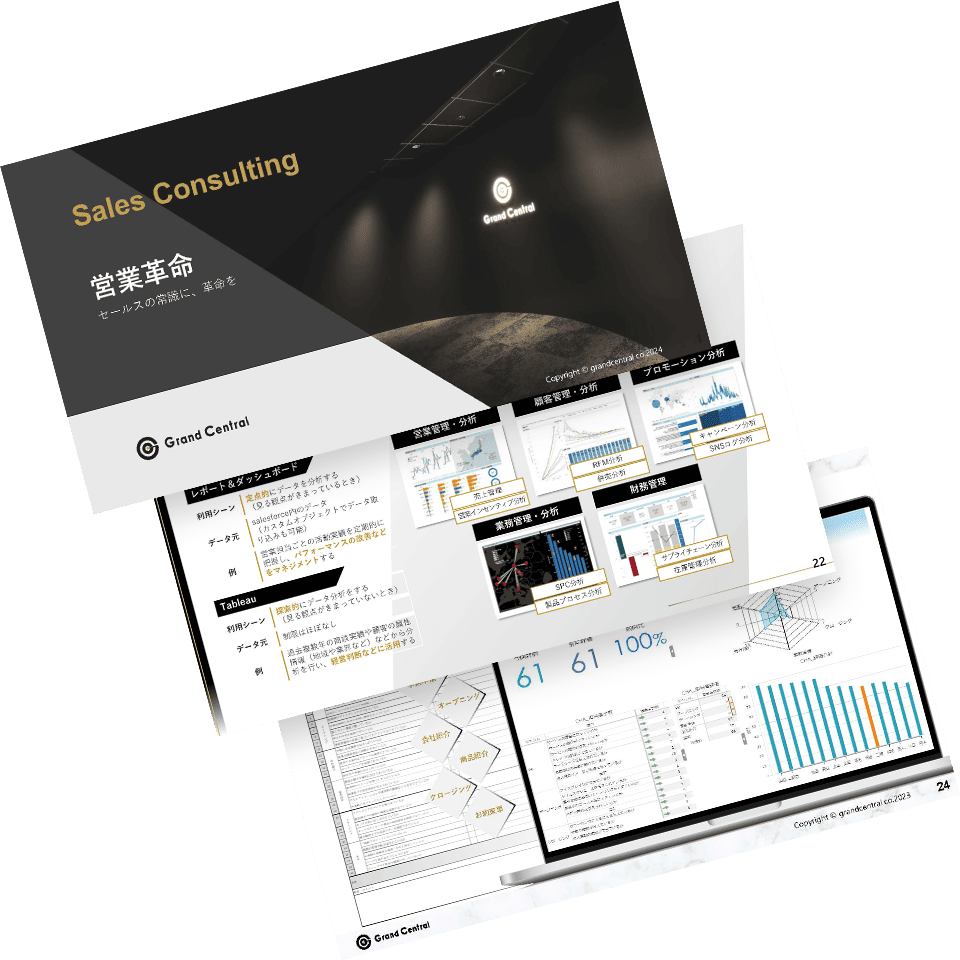営業代行は「やめとけ」と言われる7つ理由とは?失敗しない選び方を解説

営業代行を導入する場面では、「本当に成果が出るのか」「自社の営業力が落ちないか」といった懸念がつきものです。判断を誤らないためには、失敗の典型例を把握し、費用対効果を確保できる基準をあらかじめ持っておくことが重要です。
この記事では、「営業代行はやめとけ」と言われる背景と代表的な失敗要因を整理し、営業代行を利用するメリットや向いている企業、選ぶ際のポイントまで解説します。
営業代行を検討する際に陥りやすい失敗を避け、成果を最大化するためのヒントとしてご参考ください。
この記事を監修したコンサルタント

目次
営業代行が「やめとけ」と言われる7つの理由

- 費用対効果が見合わず成果が出にくい
- 自社に営業ノウハウが蓄積されない
- 営業活動の進捗や質が見えにくい
- 契約条件と成果の期待値にズレが生じやすい
- 担当者のスキルや対応にバラつきがある
- 商材によっては代行が適さないケースがある
- 情報漏洩やブランド毀損などリスクがある
費用対効果が見合わず成果が出にくい
「やめとけ」と言われる中で特に多い理由として、高額な費用を支払ったにもかかわらず、期待した成果につながらないケースが挙げられます。
固定報酬型の契約では、業者側の活動量は安定しやすい一方で、アポイントの「質」は事前の取り決めに左右されます。また、成果報酬型であっても「アポ1件獲得につき〇円」といった契約では、決裁権のない担当者との面会や、ニーズのない企業へのアプローチまで成果に含まれてしまうケースが少なくありません。
こうした失敗をしないためには、契約段階で「商談化率」や「有効商談の定義」を具体的に話し合い、短期間のテスト導入から開始するのが有効です。事前の確認を慎重におこない、効果を見極めることで、費用対効果が合わない事態を避けられます。
自社に営業ノウハウが蓄積されない
「営業代行はやめとけ」の意見の中には、契約終了後に自社の営業力が以前より低下してしまうリスクを指摘するケースも見受けられます。
営業代行業者がどのようなトークスクリプトで、どのターゲット層にアプローチして成功したのかのプロセスがわからないと、営業ノウハウは社内に蓄積されません。その結果、営業代行との契約終了後、自社で営業する際に成約まで結びつかず、営業代行なしでは継続できない状況に陥るおそれがあります。
営業代行に依存しないためには、営業代行を協業パートナーと位置づけ、定期的にミーティングをおこない、成功事例や顧客からのフィードバックを共有する体制を整えることが重要です。さらに、獲得した商談に自社の若手社員が同席し、現場のスキルを実践的に学ぶ機会を設けるのも効果的です。
営業活動の進捗や質が見えにくい
月次レポートで「アプローチ件数1,000件」の数字だけが報告されるだけ、といった活動報告があいまいな営業代行会社を選ぶと、日々の業務進捗や課題をリアルタイムで把握できず、改善の打ち手を講じる機会を逃してしまうおそれがあります。
リストの質や具体的なアプローチ手法、顧客からの反応などの重要な情報が見えなければ、適切な評価は困難です。最悪の場合、市場で自社の評判を損なうような営業がおこなわれている可能性もあります。
このような事態を避けるため、契約時には週次での定例ミーティングや、具体的な活動ログを含む詳細なレポート提出などを取り決めておくことが重要です。可能であれば、「SFA(営業支援システム)」や「CRM(顧客関係管理システム)」を共有し、リアルタイムで活動状況を可視化できる体制を構築することが理想的です。
契約条件と成果の期待値にズレが生じやすい
依頼側と営業代行会社の間で成果に対する認識がズレていると、「想定していた成果と実際の成果が大きく違う」といった後悔につながりかねません。こうした問題の根本原因として、アポイント・リード・商談化など、営業の専門用語の定義があいまいなまま契約を進めてしまうことが考えられます。
依頼側は「受注確度の高い見込み顧客との商談」を期待していても、代行会社は「担当者と話せただけ」をアポイントの成果として数える場合もあります。ズレが生じると、レポート上の目標達成率は高いのに、実際の売上は伸びない事態に陥る可能性があります。
契約書には定量的なKPIだけでなく、「アポイント=決裁権のある担当者と30分以上の商談」など、成果の定義を具体的に明記することが重要です。
担当者のスキルや対応にバラつきがある
営業代行は担当者の力量に依存する部分が大きく、経験や業界知識の差によって成果が変わります。実際、契約当初は経験豊富な営業が担当していたものの、途中で退職や交代により経験の浅いスタッフに切り替わり、成果が落ちてしまう事例は珍しくありません。
こうしたリスクを避けるには、契約前に実際に担当するメンバーやチームのスキル・経験を確認し、交代が生じた場合の対応ルールを契約段階で取り決めておくことが重要です。
商材によっては代行が適さないケースがある
営業代行の利用で成果を出せるかどうかは、商材の特性に左右されます。自社の製品やサービスに代行手法が合わなければ、期待した成果は得られません。こうしたミスマッチは「営業代行はやめとけ」と言われる大きな理由のひとつです。
以下の表を参考に、自社の商材がどちらの特徴に該当するか確認してみましょう。
|
営業代行に向いている商材 |
営業代行に向いていない商材 |
|
|
ターゲット |
ターゲット顧客が明確でリスト化しやすい |
ターゲットが不明確・ニッチすぎる |
|
営業プロセス |
営業手法を標準化・マニュアル化しやすい |
担当者個人の高度な専門知識や経験が必須 例:医療機器販売 |
|
価格・利益率 |
単価が高く、十分な利益率を確保できる |
単価が低く代行費用で赤字になる 例:汎用的なパソコン、事務用品 |
|
商談サイクル |
短期で意思決定されやすい |
長期的な信頼関係の構築が不可欠 例:保険商品 |
情報漏洩やブランド毀損などリスクがある
営業の代行業者が成果を焦るあまり、コンプライアンスを軽視した強引なテレアポを繰り返したり、顧客情報をずさんに扱ったりした場合、最終的な責任は依頼主である自社が負うことになります。こうした事態が続けば、業界内での評判悪化や情報流出といった問題に発展しかねません。
こうしたリスクを避けるには、機密情報の取り扱いについて契約締結前に細部まで確認しましょう。また、営業スクリプトを事前に共有し、承認するプロセスを設けることも、ブランド毀損リスクの有効な防止策になります。
営業代行を活用するメリット

- 即戦力で新規開拓がスピーディーに進む
- 採用・教育コストをかけずに営業体制を構築できる
- コア業務に社内リソースを集中できる
- 自社にない営業知見やナレッジを取り入れられる
即戦力で新規開拓がスピーディーに進む
営業代行を活用するメリットは、プロの営業チームを即戦力として確保し、事業の立ち上げや新規市場の開拓を圧倒的なスピードで進められる点です。自社で営業担当者を採用する場合、採用活動から研修を経て、独り立ちして安定した成果を出すまでには数ヵ月単位の時間がかかります。
営業代行であれば、契約後すぐにプロによる営業活動を開始できるため、時間を大幅に短縮できます。特に新製品のリリースや競合が少ない市場への参入など、スピードが成功を左右する場面では、機会損失を防ぐための効果的な戦略といえるでしょう。
採用・教育コストをかけずに営業体制を構築できる
質の高い営業体制の構築には、多大なコストとリスクが伴います。正社員を一人雇用すると、給与や社会保険料といった直接的な費用だけでなく、求人広告費、研修費用、備品代やマネジメントコストも発生します。また、時間と費用をかけて育成した人材が早期に退職してしまうリスクも考えられるでしょう。
営業代行を活用すれば、採用や教育にかかるコストを抑えられます。その結果、必要な時に安定して営業リソースを確保できるようになります。
コア業務に社内リソースを集中できる
企業の成長を加速させるには、限られた社内リソースをもっとも付加価値の高い業務に集中させることが重要です。たとえば、新規アポイントの獲得を外部のプロに委託することで、自社のエース社員は大型案件の商談やクロージングといった「その人でなければならない仕事」に専念できるようになります。
これまでエース級の営業担当者がテレアポに費やしていた時間を、より戦略的な活動に振りわけることで、組織全体の生産性は向上します。得意な人が得意な業務をおこなう分業体制は、売上向上だけでなく、社員のモチベーション維持にもつながるでしょう。
自社にない営業知見やナレッジを取り入れられる
プロの営業代行会社は、多様な業界や商材で培った成功実績や、最新の営業ツールに関する知識、効果的なトークスクリプトなど、体系化されたノウハウを豊富に保有しています。
これまで自社になかった新しいアプローチ手法や市場のニーズを学ぶことで、組織全体の営業力の底上げにつながります。代行業者を単なる外部リソースではなく、コンサルティングパートナーと位置づけ、定例報告会などで成功要因をヒアリングする姿勢が重要です。
キーエンスやSalesforce出身のプロフェッショナルが集結する「Grand Central」では、350社以上のプロジェクトで培った知見を単なる外注にとどめず、自社の資産に変える仕組みを整えています。Grand Centralがどのようにして実現しているのか、具体的なサービス内容については、ぜひ以下よりご覧ください。
Grand Centralの『セールスデベロップメント』の詳細はこちら
営業代行が向いている企業の特徴

- 営業リソースや経験が不足している
- 人手不足で内製化が難しい
- 短期的に成果を求めている
リスクやメリットを踏まえた上で、これから解説する特徴に自社が当てはまるかを確認することで、営業代行を導入すべきか的確な判断が可能になるでしょう。
営業リソースや経験が不足している
社内に専門の営業部署がなく、効果的な営業プロセスやノウハウが確立できていない企業は、営業代行の活用をおすすめします。営業組織をゼロから構築するには、戦略設計から人材採用、KPI管理まで専門的な知識と多くの時間が必要なためです。
技術や製品力に強みがあっても、営業ノウハウや販路の構築経験が不足していると、市場で成果を上げることは難しくなります。特にスタートアップなど限られたリソースで成長を急ぐ企業にとって、営業代行は事業を軌道に乗せるための有効な選択肢となります。
人手不足で内製化が難しい
優秀な営業人材の採用に苦戦し、慢性的な人手不足により営業活動ができていない企業にとって、営業代行は有効な打開策です。帝国データバンクの調査では、企業の51.4%が正社員の人手不足を課題として挙げています。
特に営業職は人材不足が著しく、獲得競争が激化しています。実際に営業職の有効求人倍率は2倍を超えることもあり、求職者1人に対し、2社以上が競合する採用難の状況です。
不確実な採用を待つよりも、必要な時に即戦力を投入できる方が機会損失を避けられるでしょう。こうした判断が事業計画を前に進める戦略的な経営判断といえます。
短期的に成果を求めている
下記のように、短期間で明確な数値を出す必要がある場面では、営業代行の活用が有効です
- 新製品の市場投入
- 新規事業の立ち上げ
- 特定のキャンペーン期間
日常業務を抱える営業チームにとって、短期的なプロジェクトへ十分な人員を回すのは容易ではありません。そこで営業代行を活用すれば、特定のミッションに特化した専門チームを編成し、短期間で集中的にターゲットへアプローチできます。
たとえば「3ヵ月後の大規模展示会までに、見込み顧客のリストを100件獲得する」といった目標に対応が可能です。スポットで依頼することで、自社の体制を大きく変更することなく、コストを抑えながら目的達成が可能になります。
営業代行の基本的なメリットや会社選びのポイントについては、以下の記事で網羅的に解説しているので、あわせてご覧ください。
営業代行とは?代行内容やメリット、会社選びのポイントを解説!
営業代行で選ぶ際に失敗しないポイント

- 同業界での実績・事例があるかどうか
- 料金体系と成果イメージが明確かどうか
- 営業プロセスが可視化・共有されているかどうか
- 報告頻度や定例ミーティングが設けられているかどうか
- 担当者のスキル・対応力・相性が適切かどうか
同業界での実績・事例があるかどうか
特に確認したいのが自社と同じ業界での成功実績です。業界特有の専門用語や商習慣、ターゲット顧客の特性への理解がなければ、顧客の心に響く効果的なアプローチはできません。たとえば、IT分野での実績ばかりを持つ会社に、伝統的な製造業の営業を依頼しても、業界特有の商習慣を理解できず成果につながりにくいでしょう。
信頼できる営業代行会社は、これまでの実績を明示しているケースが多いです。公式サイトや資料で公開されているかを確認し、不明な点があれば担当者に直接尋ねてみるとよいでしょう。
料金体系と成果イメージが明確かどうか
料金体系が明瞭であることはもちろん、何をどのような状態になったら成果とみなすのか、双方の認識を契約前に完璧にすり合わせることが極めて重要です。「アポイント獲得」「商談化」といった言葉の定義は会社によってさまざまで、定義があいまいなまま契約すると、成果報酬の支払いをめぐってトラブルに発展する恐れがあります。「アポイントは〇〇部門の課長職以上と30分以上のオンライン商談が設定できた状態を指す」など、口頭での確認だけでなく、誰が読んでも誤解しないレベルで契約書に明記しましょう。
営業プロセスが可視化・共有されているかどうか
営業代行を選ぶ際は、営業プロセスをどこまで明確に開示してくれるかを確認しましょう。たとえば、どのリストに対して、どのようなトーク内容でアプローチしているのかを可視化・共有できる会社は信頼できます。一方で、プロセスが見えない丸投げ状態では、ブランドイメージを損なったり、契約終了後に自社にノウハウが残らなかったりする危険があります。
実際に成果を上げている企業では、SFA(営業支援システム)やCRM(顧客管理システム)を共有し、活動状況や顧客の反応をリアルタイムで確認できる体制を整えています。こうした透明性のある仕組みが、リスクを抑えながら営業ノウハウを社内に蓄積するために有効です。
報告頻度や定例ミーティングが設けられているかどうか
契約後は、共に走りながら改善し続ける関係性を築けるかが重要です。市場や顧客の反応は常に変化するため、定期的な接点がなければ、PDCAサイクルが回らず、成果が出ないまま時間と費用だけが無駄となってしまいます。そのため、最低でも「週1回の定例報告」を契約条件に盛り込んでいるか確認しましょう。その際は単なる数値報告だけでなく、次のアクションプランや現場での気づきまでをセットで報告してもらうのがポイントです。
「毎週金曜の夕方に、指定のフォーマットで活動報告を共有してもらう」といった具体的なルールを決めておくことで、後の管理工数とリスクを軽減できます。
担当者のスキル・対応力・相性が適切かどうか
営業代行の成果を左右する最大の要因は、会社の知名度や実績ではなく「担当者そのもの」です。どれだけ立派な看板を掲げていても、実際に動くのは現場担当者であり、そのスキルや姿勢によって結果が大きく変わります
契約前の営業担当は優秀でも、契約後にアサインされた現場担当の力量が不足しているケースも少なくありません。可能であれば契約前に実際の担当者と面談し、自社商材の強みをどう伝えるかなどを質問しながら、スキルや熱意を見極めましょう。
以下のチェックポイントを参考に、パートナー選びに役立ててください。
|
パートナー選びのためのチェックポイント |
なお、以下の記事では、より具体的に自社に最適な営業代行会社を選ぶためポイントについて解説していますので、あわせてご覧ください。
営業代行で成果を出すために必要な準備

- 自社の営業課題や目標を言語化する
- 自社の優先事項を踏まえて選定基準を明確にする
- 営業代行に任せる業務範囲を明確にする
1.自社の営業課題や目標を言語化する
営業代行会社に問い合わせる前に、自社の課題と目標を定量的に言語化しておくことが重要です。準備が不十分なまま依頼すると、最適なパートナーを選べず、契約後の成果も測れなくなり、費用だけがかかる結果になりかねません。たとえば、「現在の商談化率10%が課題。3ヵ月でこれを20%に引き上げ、月15件の有効商談を創出する」というように、現状(現在地)、課題、目標(目的地)、期間を明確にしましょう。
2.自社の優先事項を踏まえて選定基準を明確にする
解決したい課題と目標が明確になったら、次に自社がパートナーに何を求めるのか、優先順位をつけた選定基準リストを作成します。自社の優先順位がなければ、各社の提案を客観的に比較できず、知名度や営業トークの上手さといった本質的でない要素で判断してしまうリスクがあります。そのため、下記のように自社の状況に合わせて基準を設けることが重要です。
- 業界での実績を最優先:多少コストが高くても専門業者へ依頼
- コストを最優先:成果報酬型で対応してくれる業者を検討
基準に沿って各社を点数化すれば、納得感を持って最適なパートナーを選べます。
3.営業代行に任せる業務範囲を明確にする
営業代行の失敗として典型的なのが、業務範囲のあいまいさが原因で起こるトラブルです。どの部分を委託し、どこからを自社で担当するのか、業務の範囲と責任の所在を事前に明確に切り分ける必要があります。
たとえば、以下のように具体的な役割分担を決めます。
|
担当 |
業務範囲 |
|
代行会社 |
|
|
自社 |
|
また、「CRM(顧客関係管理システム)」の入力ルールや、Webからの問い合わせ(インバウンドリード)への対応方法なども事前にすり合わせておきましょう。準備しておくことで、契約後のスムーズな連携体制と、責任感のある協業関係の構築につながります。
ただし、そもそも「どの業務を委託すべきか」と悩んでいる企業には、多くの場合、自社の営業リソース不足という根本的な課題があります。営業代行の活用は有効な打ち手のひとつですが、他にも選択肢は存在します。
以下の資料では、リソース不足を解決する6つの打ち手について詳しく解説していますので、ぜひご活用ください。
資料ダウンロードDownload
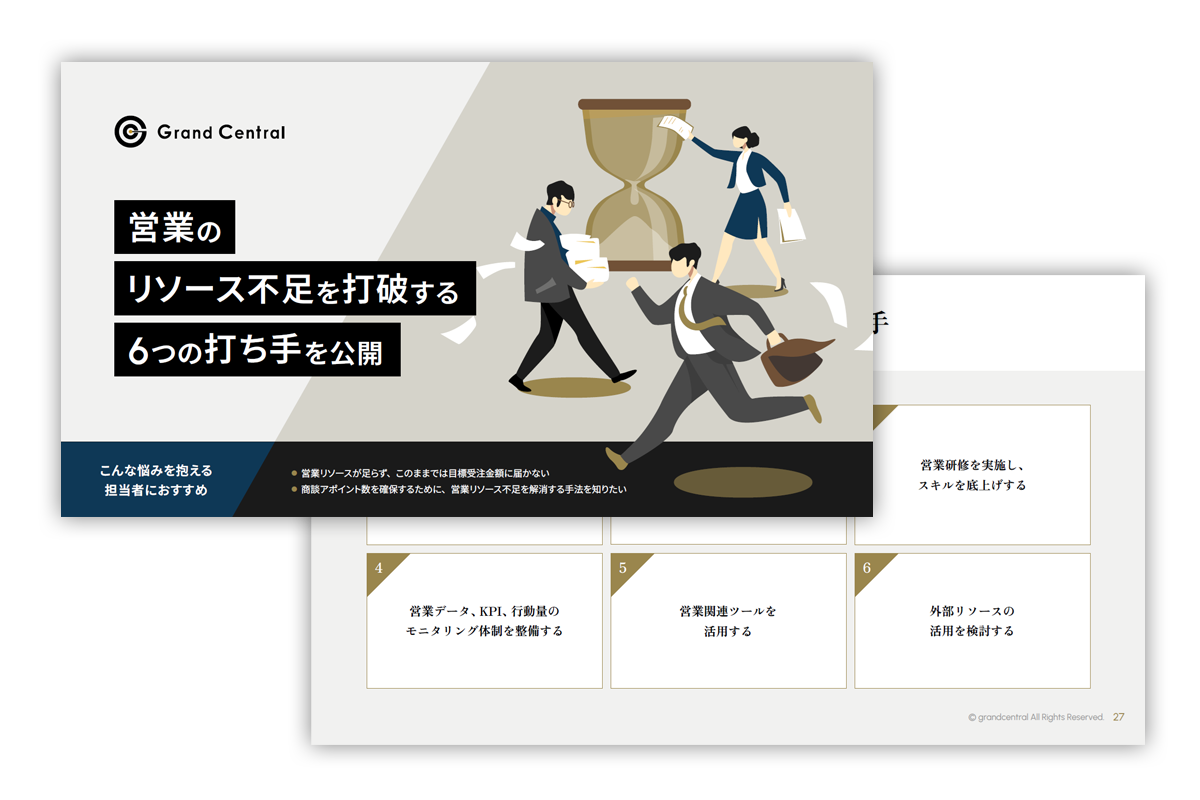
Grand Centralができること
成果につながる営業活動には、代行の実行力とコンサルティングの戦略性を兼ね備えた支援が欠かせません。そこで、弊社Grand Centralが提供するサービスをご紹介します。
Grand Centralが提供するセールスデベロップメントとは
Grand Centralのセールスデベロップメントは、単なるアポイント獲得代行ではなく、営業戦略の立案から実行、検証までを一貫して支援するサービスです。
営業代行でよくある失敗は、戦略と実行の分断にあります。Grand Centralのセールスデベロップメントは、その両方を一貫して担うことで、成果の質に直結する支援を提供しています。以下では、その具体的な特徴をご紹介します。
Grand Centralならではの3つの特徴
徹底したプロセスの可視化
クライアント様との信頼関係をもっとも重要視し、ブラックボックスになりがちな業務をCRMなどを通じて完全にオープンにします。これにより、「活動の進捗や質が見えにくい」「ノウハウが自社に蓄積されない」といった失敗を防ぎます。プロセスの透明性を確保することで、リアルタイムでの状況把握と、契約終了後も貴社に「勝ち方パターン」の資産が残る体制が構築可能です。
オーダーメイドの戦略設計
キーエンス、リクルートなどでトップレベルの営業を経験したプロフェッショナルが、貴社の業界や商材、顧客特性を徹底的に分析し、戦略をゼロから設計します。このアプローチにより、「商材によっては代行が適さない」というミスマッチや、「担当者のスキルにバラつきがある」といったリスクに根本から対応します。
成果の「質」へのコミット
契約前に決裁権の有無や予算状況といった条件をクリアした「有効商談」の定義を貴社と明確にすり合わせ、その創出をKPIとしてコミットします。これにより、費用対効果が見合わない、契約条件と成果の期待値にズレが生じるという、致命的な失敗を防ぎます。
Grand Centralのご支援実績
ここでは、代表的なご支援実績を3つご紹介します。
Sansan株式会社様
Sansan株式会社様は、イベント事業の新領域において短期で結果に結びつける必要がありました。Grand Centralはセールスのプロ集団として、圧倒的なスピード感でPDCAを回し、柔軟な契約形態で施策の効果検証を加速させました。
その結果、「Grand Centralなくして、今回のイベントの成功はなかった」と高い評価をいただいています。
株式会社ドコモ・バイクシェア様
株式会社ドコモ・バイクシェア様は、サービスの拡販において社内の営業リソースに限りがあり、外部支援を検討していました。Grand Centralは、前例のない市場環境でも現場の声を吸い上げながら改善提案を行い、徹底した案件・進捗管理を実施。これにより契約件数を着実に増加させました。
こうした取り組みが評価され、創業当初から現在まで長期にわたるパートナーシップが続いています。
株式会社オロ様
株式会社オロ様は、クラウドERP「ZAC」の拡販において、目標商談数が不足しており、過去に依頼した他社の営業代行ではリード獲得にとどまり十分な成果が得られないという課題を抱えていました。
Grand Centralは明確なKPIを設計し、アポイントの「質」にまで踏み込んだ活動を展開。状況に応じた多様なアプローチや新しい施策を次々と提案し、商談創出に直結する取り組みを実施しました。
その結果、商談数は大幅に増加し、アポイントの質も向上。継続してご依頼いただく中で稼働の幅も広がり、長期的なパートナーシップとしてご支援が続いています。
まとめ

営業代行を選ぶ際に重要なのは、料金体系や実績の確認はもちろん、営業プロセスを共有し、共に成果を目指せるパートナーを選ぶことです。この記事で紹介した選定ポイントや準備を参考にし、自社の事業成長を加速させる最適な一社を見つけてください。
以下の資料では、営業活動で直面しやすい課題に対して、Grand Centralがどのように解決策を提供できるのかを具体的にまとめています。パートナー選定の際に、比較検討の材料としてご活用ください。
資料ダウンロードDownload